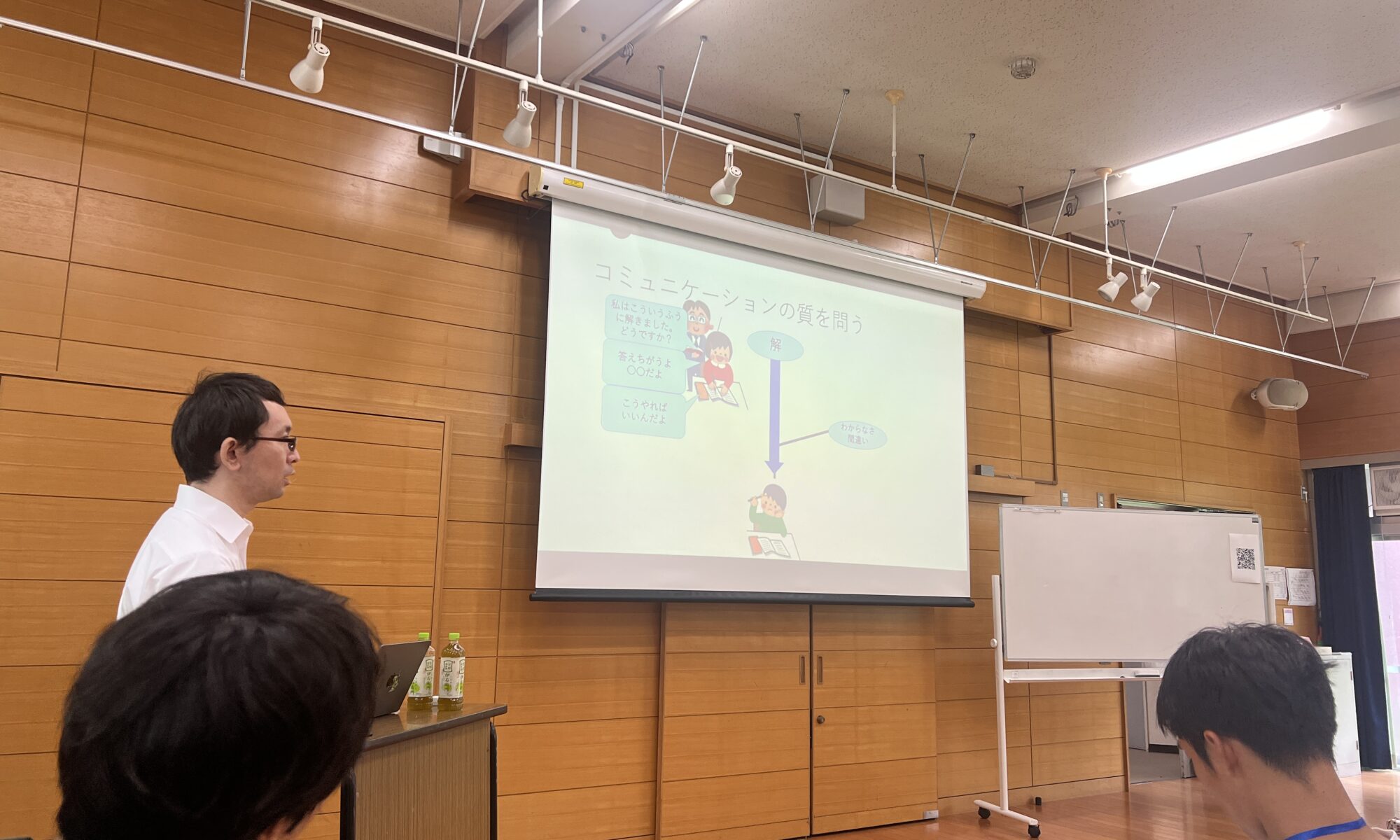東京大学の一柳智紀さんから「コミュニケーションの質」について学ぶ機会があり、その内容は今後の自分のワークショップ授業におけるピア・カンファランスの質を高めるうえで大きな示唆となりました。ここでは、その学びを整理して共有してみます。
私たち教師は、授業中に「間違ってもいいよ」と言いながらも、「できた人は?」「わかった人、教えてくれる?」と問いかけてはいないでしょうか。この問いかけは無意識のうちに「できた子」に焦点を当ててしまいます。その結果、いままさに考えの途中にいる子や「わからない」と感じている子にとって、「間違ってもいいよ」という言葉は空語になってしまいます。授業は誤りを資源として扱いながらゴールへ向かう営みです。しかし、1時間単位で成果を求められる圧力の中では、つい「わかった人に説明してもらう」ことで授業を前に進めがちです。そのとき置き去りになっているのは、「もっと考えたい」「じっくり悩みたい」と願う子どもたちです。
ここで、教室の対話を二つの型で捉え直す必要があります。一柳さんの研究によると、整理され磨かれた考えを明瞭に伝えるやりとりを「発表的会話」と呼びます。たとえば「ここは7と6を足す。繰り上がりを直せば13だよ」というように、筋道だった説明を一方向に提供する場面です。思考の整理や共有、まとめには大きな価値がありますが、子ども同士のやりとりが「正答の発表会」にとどまり、思考のプロセスを共に辿らないと、学びが浅くなりやすいという側面があります。
一方で、未完成の考えを試し合い、互いに補い合いながら進むやりとりを「探索的会話」と呼びます。「うーん、違うかな」「ここ72でかけるんじゃない?」「ここを16にして…」「これ埋めるんだけど」「そうそう、埋めて…それで戻すときに引く?」といった、言い淀みや仮説的な表現を含みつつ、プロセスを共有し合う会話です。結論より過程が往復し、根拠を出し合い、誤解が修正され、新しい見方が立ち上がります。探索的会話があるとき、子どもたちの思考は豊かに広がり、深まっていきます。
重要なのは、どちらが優れているかではなく、役割の違いを踏まえて意図的に併用することです。発表的会話は思考を整え、伝える力を育てます。探索的会話は考えを生み、共に創る力を育てます。ところが多くの教室では、時間的制約や評価の枠組みの影響で発表的会話に偏りがちです。だからこそ、授業デザインの中に「未完成の考えを出してよい時間」と「まとめて伝える時間」を明確に位置づけ、行き来できるようにすることが大切だと考えられます。
このとき土台となるのが「聴く文化」です。聴くとは、単に相手を見て頷く作法ではなく、相手の言葉に応答し、問い返し、言い直しを支える実践です。「わからない」とつぶやいた声に、隣の子が「こういうこと?」と代弁し、さらに別の子が根拠を足す。こうした経験が重なるほど、子どもたちは安心して未完成の考えを口にできるようになります。教師もまた、子どもの発話に即座に評価を与えるのではなく、「いまの『わからない』はどこから来ているの?」と問い、プロセスを一緒に確かめる聴き手でありたいと思います。
理解の到達を子どもと共有する指標として、「わかる」のスケールを次のように示すことができます。
1 わかっている
2 わかっていることを説明できる
3 わかっていることを教えることができる(多くはここで止まりがちです)
4 わかっていることで、わからない人の問いに応じて援助できる
この「4」に届いたとき、教室の学びは真に協働的になります。小さな声や不安な声が仲間に支えられ、代弁や言い直しを通して言葉になっていく場面を、意図的に設計していきたいのです。
発表で思考を整え、探索で思考を広げる。この往還を授業に組み込み、聴き合う文化を育てることで、子どもたちは互いの考えに働きかけながら学びをつくっていけます。評価や時間の制約に押されて「できた人」中心の進行に戻りそうになったときこそ、「未完成の考えが歓迎される時間」と「まとめて伝える時間」の二つを思い出し、両輪で授業を設計していくことが大切なのです。これが、ピア・カンファランスの質を底上げし、教室全体の学びを一段深める道筋になると考えられます。